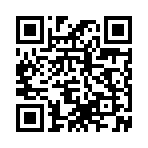2013年08月25日
南アルプス 仙丈ヶ岳 大展望トレッキングに行った!
8月3日 山梨県と長野県に跨る 南アルプス 仙丈ヶ岳 にトレッキングに行ってきました。

今年トレッキングを始めて登ろうと決めていたのが 仙丈ヶ岳でした。
長野県に10年ほど前に住んでいた頃、仕事の担当先が宮田村(伊那市と駒ヶ根市の隣町)にありました。
その得意先の営業唐木さんと同行営業をよくしていたのですが、伊那谷(南アルプスと中央アルプスの間の盆地で辰野、伊那、駒ヶ根などの町がある場所です)から見える南アルプスの山々が本当に綺麗で、東京から転勤で長野に越してきて山の名前も分からなかった私は、同行中に唐木さんにあれは?それは?と聞いて教えてもらいました。
一番大きく見えて迫力があったのが、仙丈ヶ岳で、その左側に甲斐駒ケ岳、右側に北岳が連なって、特に冬の景色は素晴らしいものでした。当時50歳は超えていた唐木さんは中学生の頃学校登山で登ったこともあると話していました。
■宮田の会社の施設から見た仙丈ヶ岳
右は北岳です

その唐木さんは ある時不慮の事故で亡くなってしまいました。あまりに突然のことで驚き、悲しみは後から感じるようになりました。
会社の施設が宮田にあることもあり、今だに年数回 伊那谷を訪れる私は、毎度仙丈ヶ岳を見ると唐木さんを思い出すのでした。
それが理由で、山を登るなら 仙丈ヶ岳を登ろうと決めていたのです。

今年トレッキングを始めて登ろうと決めていたのが 仙丈ヶ岳でした。
長野県に10年ほど前に住んでいた頃、仕事の担当先が宮田村(伊那市と駒ヶ根市の隣町)にありました。
その得意先の営業唐木さんと同行営業をよくしていたのですが、伊那谷(南アルプスと中央アルプスの間の盆地で辰野、伊那、駒ヶ根などの町がある場所です)から見える南アルプスの山々が本当に綺麗で、東京から転勤で長野に越してきて山の名前も分からなかった私は、同行中に唐木さんにあれは?それは?と聞いて教えてもらいました。
一番大きく見えて迫力があったのが、仙丈ヶ岳で、その左側に甲斐駒ケ岳、右側に北岳が連なって、特に冬の景色は素晴らしいものでした。当時50歳は超えていた唐木さんは中学生の頃学校登山で登ったこともあると話していました。
■宮田の会社の施設から見た仙丈ヶ岳
右は北岳です

その唐木さんは ある時不慮の事故で亡くなってしまいました。あまりに突然のことで驚き、悲しみは後から感じるようになりました。
会社の施設が宮田にあることもあり、今だに年数回 伊那谷を訪れる私は、毎度仙丈ヶ岳を見ると唐木さんを思い出すのでした。
それが理由で、山を登るなら 仙丈ヶ岳を登ろうと決めていたのです。
今回の登山もKさんと登りました。
金曜日の夜10時半に横浜からKさんに南大沢にきて頂き、南アルプスの登山の登り口にあたる北沢峠に向かうバス乗り場の(環境保護でマイカーでは峠には行けません)芦安(山梨南アルプス市)に向かいます。静岡側、長野側にもバスの発着場がありますが、東京からだと芦安が一番アクセスがよいです。
八王子インターから甲府昭和インターまで高速を使い、そこから一般道で芦安の市営駐車場へ約40分くらいです。芦安温泉で検索すると分かりやすいです。
途中で食事をしたので 到着は2時前くらいでした。
市営駐車場は第1から第8まであり、他に臨時もありますが、北沢峠に向かうバスの発着場に近いのは第2と第3です。
ですが…到着時間の段階では駐車場はすでに満車!1〜4まではびっしりです。少し離れた第5駐車場にようやく停めることができました。みなさん、金曜日夜によく早くに到着できますね。羨ましい。
■第5駐車場の朝
道路に縦列駐車も沢山でした。

朝4時半に起きて(またもや超寝不足)準備をして第2駐車場前の路線バス乗り場に向かいます。トイレは第3駐車場にありました。
すでに凄いバス待ちの列が…(ーー;)
まずは切符を買って列に並びます。

5時30分に始発バスが出発しますが、全員のれるように大量のバスが一斉に発進します(^^)

団体で行く場合などは乗り合いジャンボタクシーもあるので予約しておくと良いみたいです。
芦安からはまず、広河原バス停まで行くことになります。北沢峠への直通はありません。それでも広河原まで約1時間も時間がかかります。途中で夜叉神峠に一時停車します。夜叉神峠からは鳳凰三山への登山道が伸びています。
広河原で降りると、またもや切符を買う長い列が(ーー;)
広河原からは日本2番目の高さの北岳への登山道が伸びていますのでそちらに向かう人も沢山いました。

ここでマイクロバス乗り換え北沢峠まで約30分。深い谷沿いの道を進んで7時15分すぎにようやく到着!
7時30分にバス停横のトイレ脇の登山口から仙丈ヶ岳を目指します。北沢峠の標高は2000mです。
■北沢峠の風景



1合目〜5合目までは樹林帯をひたすら登って行きます。展望はききませんが気持ちの良い登山道です。


5合目の大滝頭に9時到着。
ここから、小仙丈ヶ岳経由のコースと馬の背経由の登山口に分かれますが私たちは小仙丈ヶ岳方面へ向かいます。

5合目を過ぎ勾配がきつくなってきますが、その辺りで後ろを振り返ると ご覧の景色が!
■甲斐駒ケ岳と鋸山(^-^)/

摩利支天(右のコブ部分)も見えました

この日は天気予報では曇り又は霧 一時晴だったので心配でしたが雲海と流れる雲の中で迫力ある甲斐駒ケ岳が見れて良かったです。
その後森林限界を迎えると小仙丈ヶ岳を見上げる景色が待っています。

展望が開けて気持ちが良いです。
この日の天気は15度くらいで登山には良かったのですが、森林限界を超えると直射日光もあり20度くらいに上がりました。
登り切ると、ようやく小仙丈ヶ岳に10時10分到着です。やった〜!(^-^)/
■小仙丈ヶ岳 2855m

駒ヶ岳は雲の中に。さっき見れてよかった。 南側には北岳が見えました(写真なし)
そして小仙丈ヶ岳からは、私が仙丈ヶ岳で一番楽しみにしていた 小仙丈沢カールの大展望がバッチリ見ることができました!これだけで もう大満足です。最近の登山では天気に恵まれなかったので本当に嬉しかったです。
■小仙丈ヶ岳から見た小仙丈沢カール

本当に良い景色です。

このあと、尾根沿いに仙丈ヶ岳を目指して登っていきます。

一度登り切って山頂かな?と思ったら最後の登りが待っています。仙丈ヶ岳は何回かのピークを超えて行くような山です。でもこの辺りの山歩きはとても気持ちが良いところでした。


そしてついに仙丈ヶ岳 山頂へ到着です!
到着時間は11時30分ころ。休憩時間も入れて4時間でした。南アルプスの入門編と言われている山ですが、標高差1000mの登りは大変でした。
■仙丈ヶ岳 3033m

この日は行きませんでしたが、大仙丈ヶ岳も見ることができました。
山頂では昼食とし、のんびり休憩を取りました。私は3000mの山は始めてだったのですが、空が近い!やっぱり気持ちいいですね。
その後、唐木さんへ持ってきた「いいちこ」を山頂の岩にかけ、自分も一口飲みました。運良く、伊那市方面の街並みが雲の間から見ることができました。
■雲海といいちこ。

お昼ご飯を食べしばらく休憩してから、下山を始めました。
山頂からは直下の仙丈小屋を経由して、馬の背ヒュッテを経て 5合目大滝頭へ周回する形で北沢峠に降りるコースです。
仙丈小屋は山頂のすぐ下に位置しており、綺麗な山小屋です。トイレ(有料)を借りました。一度宿泊してみたいですね!
■仙丈小屋

バンダナを買いました(^^)

小屋の下には水場があり、ものすごい冷たい美味しい水が出ていました。

そしてここから本格的に下山となるのですが、懸案の膝裏痛が発症…
実は小仙丈ヶ岳を過ぎた頃から 少しだけ違和感を感じていたのですが、下りに入ってから一気に痛みが出てしまいました。一応サポーターは付けましたが、私の痛みはひざ裏で、一度痛くなり始めると歩くのをやめない限りどんどん痛みが激化していくのです。
「ヤバイな…(汗)」
北沢峠まで標高差1000m近く残っています。不安が広がりました。
その不安は的中。
痛みが激痛に変わっていき、最初は右足だったのが両足に。馬の背ヒュッテに着く頃には膝を少し曲げると痛みで力が入らなくなっていました。(-_-)
(別の機会に記事を書こうと思いますが、病院の診察結果で、足全体の靭帯<筋>が硬いこと、筋力が不足していることで疲れが溜まると弱い膝に痛みが出るとのこと。出た場合はアイシングで痛みを和らげる以外は特効薬はないそうです)
後から考えればヒュッテに宿泊することにすれば良かったと思いますが、終バス時間16時までまだ3時間くらいあったので、歩行を続行。
しかし、大滝頭までには 雪渓渡りや沢渡りもあり、痛みのある私には拷問。
■雪渓渡り(下り唯一の写真です)

大滝頭からは、バスの最終時間を考えて、Kさんには先に降りて頂くことに。
私は最悪の場合 北沢峠の山小屋にお世話になるしかないと考えました。
そこから先は、もうほとんど痛みに耐えて気力の下山でした。後ろから来る登山者には全て道を譲り、なんで私だけこんなに痛くなるのかと悔しくなりながら、少しづつ降りました。正直ストックがなかったら体を支えられず下山できなかったと思います。
結局バス発車前3分前、3時57分に北沢峠に到着。なんとかバスに乗れました。
Kさんにはずいぶんと心配と迷惑をかけてしまいました。改めてお詫びとお礼を申し上げます。
ということで、登りは天国、下りは地獄の仙丈ヶ岳登山となりました。
仙丈ヶ岳は素晴らしい景色を楽しめる山で、小屋泊を含めてまた絶対に訪れたいと感じました。
反面、自分の体力に合った山登りをしなければ、我慢できない状況の場合は危険だということに改めて感じました。
危険な場所などには気を付けていましたが、距離や時間にももっと気を使わねば私の場合はNGでした。反省です。
体力トレーニングと共に、一般的なプランでの日帰りに拘らず、自分に合った小屋泊・テント泊なども上手に活用していきたいと思います。
■本日の歩行距離:9.7km
■本日の歩行時間:8時間58分
■参考
膝裏痛対策の記事は別の記事で書いています
こちら
金曜日の夜10時半に横浜からKさんに南大沢にきて頂き、南アルプスの登山の登り口にあたる北沢峠に向かうバス乗り場の(環境保護でマイカーでは峠には行けません)芦安(山梨南アルプス市)に向かいます。静岡側、長野側にもバスの発着場がありますが、東京からだと芦安が一番アクセスがよいです。
八王子インターから甲府昭和インターまで高速を使い、そこから一般道で芦安の市営駐車場へ約40分くらいです。芦安温泉で検索すると分かりやすいです。
途中で食事をしたので 到着は2時前くらいでした。
市営駐車場は第1から第8まであり、他に臨時もありますが、北沢峠に向かうバスの発着場に近いのは第2と第3です。
ですが…到着時間の段階では駐車場はすでに満車!1〜4まではびっしりです。少し離れた第5駐車場にようやく停めることができました。みなさん、金曜日夜によく早くに到着できますね。羨ましい。
■第5駐車場の朝
道路に縦列駐車も沢山でした。

朝4時半に起きて(またもや超寝不足)準備をして第2駐車場前の路線バス乗り場に向かいます。トイレは第3駐車場にありました。
すでに凄いバス待ちの列が…(ーー;)
まずは切符を買って列に並びます。

5時30分に始発バスが出発しますが、全員のれるように大量のバスが一斉に発進します(^^)

団体で行く場合などは乗り合いジャンボタクシーもあるので予約しておくと良いみたいです。
芦安からはまず、広河原バス停まで行くことになります。北沢峠への直通はありません。それでも広河原まで約1時間も時間がかかります。途中で夜叉神峠に一時停車します。夜叉神峠からは鳳凰三山への登山道が伸びています。
広河原で降りると、またもや切符を買う長い列が(ーー;)
広河原からは日本2番目の高さの北岳への登山道が伸びていますのでそちらに向かう人も沢山いました。

ここでマイクロバス乗り換え北沢峠まで約30分。深い谷沿いの道を進んで7時15分すぎにようやく到着!
7時30分にバス停横のトイレ脇の登山口から仙丈ヶ岳を目指します。北沢峠の標高は2000mです。
■北沢峠の風景



1合目〜5合目までは樹林帯をひたすら登って行きます。展望はききませんが気持ちの良い登山道です。


5合目の大滝頭に9時到着。
ここから、小仙丈ヶ岳経由のコースと馬の背経由の登山口に分かれますが私たちは小仙丈ヶ岳方面へ向かいます。

5合目を過ぎ勾配がきつくなってきますが、その辺りで後ろを振り返ると ご覧の景色が!
■甲斐駒ケ岳と鋸山(^-^)/

摩利支天(右のコブ部分)も見えました

この日は天気予報では曇り又は霧 一時晴だったので心配でしたが雲海と流れる雲の中で迫力ある甲斐駒ケ岳が見れて良かったです。
その後森林限界を迎えると小仙丈ヶ岳を見上げる景色が待っています。

展望が開けて気持ちが良いです。
この日の天気は15度くらいで登山には良かったのですが、森林限界を超えると直射日光もあり20度くらいに上がりました。
登り切ると、ようやく小仙丈ヶ岳に10時10分到着です。やった〜!(^-^)/
■小仙丈ヶ岳 2855m

駒ヶ岳は雲の中に。さっき見れてよかった。 南側には北岳が見えました(写真なし)
そして小仙丈ヶ岳からは、私が仙丈ヶ岳で一番楽しみにしていた 小仙丈沢カールの大展望がバッチリ見ることができました!これだけで もう大満足です。最近の登山では天気に恵まれなかったので本当に嬉しかったです。
■小仙丈ヶ岳から見た小仙丈沢カール

本当に良い景色です。

このあと、尾根沿いに仙丈ヶ岳を目指して登っていきます。

一度登り切って山頂かな?と思ったら最後の登りが待っています。仙丈ヶ岳は何回かのピークを超えて行くような山です。でもこの辺りの山歩きはとても気持ちが良いところでした。


そしてついに仙丈ヶ岳 山頂へ到着です!
到着時間は11時30分ころ。休憩時間も入れて4時間でした。南アルプスの入門編と言われている山ですが、標高差1000mの登りは大変でした。
■仙丈ヶ岳 3033m

この日は行きませんでしたが、大仙丈ヶ岳も見ることができました。
山頂では昼食とし、のんびり休憩を取りました。私は3000mの山は始めてだったのですが、空が近い!やっぱり気持ちいいですね。
その後、唐木さんへ持ってきた「いいちこ」を山頂の岩にかけ、自分も一口飲みました。運良く、伊那市方面の街並みが雲の間から見ることができました。
■雲海といいちこ。

お昼ご飯を食べしばらく休憩してから、下山を始めました。
山頂からは直下の仙丈小屋を経由して、馬の背ヒュッテを経て 5合目大滝頭へ周回する形で北沢峠に降りるコースです。
仙丈小屋は山頂のすぐ下に位置しており、綺麗な山小屋です。トイレ(有料)を借りました。一度宿泊してみたいですね!
■仙丈小屋

バンダナを買いました(^^)

小屋の下には水場があり、ものすごい冷たい美味しい水が出ていました。

そしてここから本格的に下山となるのですが、懸案の膝裏痛が発症…
実は小仙丈ヶ岳を過ぎた頃から 少しだけ違和感を感じていたのですが、下りに入ってから一気に痛みが出てしまいました。一応サポーターは付けましたが、私の痛みはひざ裏で、一度痛くなり始めると歩くのをやめない限りどんどん痛みが激化していくのです。
「ヤバイな…(汗)」
北沢峠まで標高差1000m近く残っています。不安が広がりました。
その不安は的中。
痛みが激痛に変わっていき、最初は右足だったのが両足に。馬の背ヒュッテに着く頃には膝を少し曲げると痛みで力が入らなくなっていました。(-_-)
(別の機会に記事を書こうと思いますが、病院の診察結果で、足全体の靭帯<筋>が硬いこと、筋力が不足していることで疲れが溜まると弱い膝に痛みが出るとのこと。出た場合はアイシングで痛みを和らげる以外は特効薬はないそうです)
後から考えればヒュッテに宿泊することにすれば良かったと思いますが、終バス時間16時までまだ3時間くらいあったので、歩行を続行。
しかし、大滝頭までには 雪渓渡りや沢渡りもあり、痛みのある私には拷問。
■雪渓渡り(下り唯一の写真です)

大滝頭からは、バスの最終時間を考えて、Kさんには先に降りて頂くことに。
私は最悪の場合 北沢峠の山小屋にお世話になるしかないと考えました。
そこから先は、もうほとんど痛みに耐えて気力の下山でした。後ろから来る登山者には全て道を譲り、なんで私だけこんなに痛くなるのかと悔しくなりながら、少しづつ降りました。正直ストックがなかったら体を支えられず下山できなかったと思います。
結局バス発車前3分前、3時57分に北沢峠に到着。なんとかバスに乗れました。
Kさんにはずいぶんと心配と迷惑をかけてしまいました。改めてお詫びとお礼を申し上げます。
ということで、登りは天国、下りは地獄の仙丈ヶ岳登山となりました。
仙丈ヶ岳は素晴らしい景色を楽しめる山で、小屋泊を含めてまた絶対に訪れたいと感じました。
反面、自分の体力に合った山登りをしなければ、我慢できない状況の場合は危険だということに改めて感じました。
危険な場所などには気を付けていましたが、距離や時間にももっと気を使わねば私の場合はNGでした。反省です。
体力トレーニングと共に、一般的なプランでの日帰りに拘らず、自分に合った小屋泊・テント泊なども上手に活用していきたいと思います。
■本日の歩行距離:9.7km
■本日の歩行時間:8時間58分
■参考
膝裏痛対策の記事は別の記事で書いています
こちら
この記事へのコメント
はじめまして・・・、ではなく2回目のコメでした。^^
結局、仙丈は夜行日帰ができるのですね。知りませんでした。
天気が良くて運がよかったですね。
たしか次の日は良くなかったと思いますが。(自分は北アルプスを登っていて雨でしたから)
ここは花の名山で、訪れてみたいと思っていたところです。
朝のバスの記事が詳しくて、たいへん参考になり助かりました。
これからも小屋やテント泊で、いろんな高い山に行かれるのでしょうね。
記事を楽しみにしています。
結局、仙丈は夜行日帰ができるのですね。知りませんでした。
天気が良くて運がよかったですね。
たしか次の日は良くなかったと思いますが。(自分は北アルプスを登っていて雨でしたから)
ここは花の名山で、訪れてみたいと思っていたところです。
朝のバスの記事が詳しくて、たいへん参考になり助かりました。
これからも小屋やテント泊で、いろんな高い山に行かれるのでしょうね。
記事を楽しみにしています。
Posted by 笹人 at 2013年09月06日 17:38
笹人さん、こんにちは(^^)
コメントありがとうございました。
仙丈ヶ岳は登山口の北沢峠までのアプローチが面倒ですが、一般の登山者の方ならば、日帰りは楽勝だと思います。ただ、終バスが16時なので、それを逃すと帰れなくなる不安がありますね(笑)
甲斐駒ケ岳も北沢峠からの登山ができ、やはり日帰りができるようですが、こちらの行程の方が厳しいみたいですね。
大分涼しくなってきましたので、低山も含めてトレッキングには良い季節が訪れますね!
コメントありがとうございました。
仙丈ヶ岳は登山口の北沢峠までのアプローチが面倒ですが、一般の登山者の方ならば、日帰りは楽勝だと思います。ただ、終バスが16時なので、それを逃すと帰れなくなる不安がありますね(笑)
甲斐駒ケ岳も北沢峠からの登山ができ、やはり日帰りができるようですが、こちらの行程の方が厳しいみたいですね。
大分涼しくなってきましたので、低山も含めてトレッキングには良い季節が訪れますね!
Posted by SANPO at 2013年09月10日 07:38
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。